
平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。
(※参照:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)相続税関係PDFファイル)
(※参照:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)国税庁ホームページ)
[改正前]
5,000万円 + (1,000万円 × 法廷相続人の人数)
↓
[改正後]
3,000万円 + (600万円 × 法廷相続人の人数)
この改正によって、相続税が身近になったという方も少なくないのではないでしょうか。
相続に関して、心得ておくべきポイントを5つまとめましたので、どうぞご確認ください。
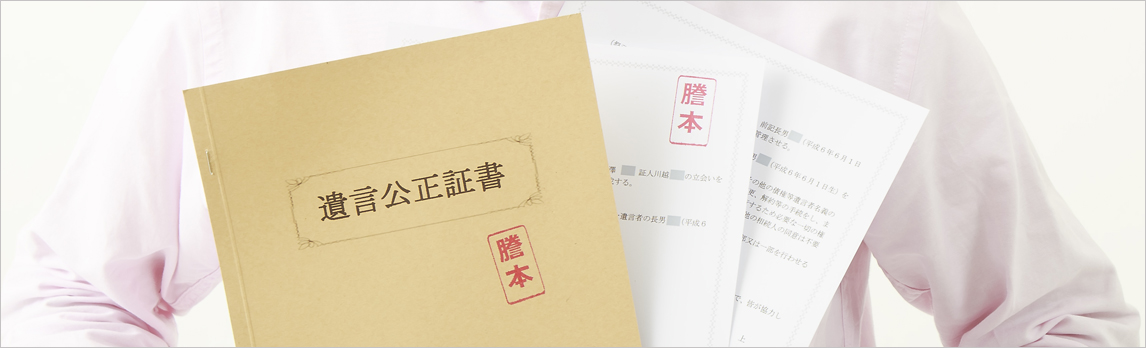
①税法上における相続財産と民法上における相続財産
税法上における相続財産とは相続税の申告にあたってその税額計算の基礎となる財産として、主として担税力(税金の支払能力)を考慮して相続税法等に定められている財産のことです。
これに対して民法上における相続財産とは、遺産分割における各相続人の相続分計算の基礎となる財産であって主として相続人間の公平性を考慮して民法に定められています。
たとえば被相続人が生命保険に加入していて、その死亡保険金の受取人が相続人のうちの誰かとされていた場合においては、この死亡保険金は税法上においては「みなし相続財産」として取扱われるのに対して、民法上はその相続人の固有の財産として取扱われ相続財産とはならないこととされています。
また相続人が被相続人から生前贈与された財産については、税法上は相続財産には含まれておらず相続税の対象とはなりませんが、民法上は相続財産として生前贈与分は相続財産への持ち戻しをすることになります。
実際に相続が開始した場合においては、まず遺産分割を進めていくために「民法上における相続財産」について調査して確定した相続人がそれぞれの相続分を受けた後に、「税法上における相続財産」によって課税される相続税について相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税することになります。
②相続の手続きの流れ
(1)遺言書の有無を確認し、公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認を受けます。
(2)法定相続人の確定(子?直系尊属?兄弟姉妹の順で相続人になり、配偶者は常に相続人になります。)
(3)相続財産の調査
(4)遺言による指定相続分がないとき、あるいは相続人全員の合意により指定相続分に従わないときは遺産分割協議を行い、それが成立したときは遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
(5)相続税が課税される場合には、相続開始を知った日から10カ月以内に申告納税します。
(6)所得税について確定申告義務のある者から相続する場合には、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に相続人が準確定申告をしなければなりません。
(7)不動産を相続した場合には、その不動産について相続登記をすることになりますが、この相続登記には期限や罰則等はないものの、遺産分割協議などにおいて重要な指標となることがあるため、遺産分割協議書の作成と併せて行っていくのが良いでしょう。
(8)預貯金を相続したときはその預貯金口座の凍結介助の手続きが必要になります。
③相続が開始したときには必ず「負債がないか」確認すること
相続をする場合には預貯金や土地・建物などの「積極財産」のみならず借金や保証債務などの「消極財産」も同時に引き継ぐことになります。
相続の方法は「積極財産・消極財産すべて相続する単純承認」「相続人全員の合意により積極財産の範囲内で消極財産を相続する限定承認」「相続放棄」の3つがありますが、相続人は、自己のために相続があったことを知ったときから基本的には3カ月の熟慮期間内に決定する必要があり、それまでに負債の有無を確認し、負債があるときは限定承認または相続放棄を家庭裁判所に申立てなければ単純承認をしたものとみなされます。
なお相続放棄をした相続人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
④遺産相続でトラブルを避けるために「遺言書」を遺すこと
相続に際して最もトラブルが発生しがちなのが、その取り分をめぐって行われる遺産分割協議です。これは主として遺言書による相続分の指定がないことが原因であるために、被相続人が遺言書を遺しておくことが肝要です。民法に定められている法定相続分などはあくまでも目安として強制されるものではなく、特別受益の相続財産への持ち戻しや寄与分による相続分の見直しが遺産分割協議に含まれてくるとますます紛糾する可能性が高くなります。
⑤遺言書を遺すときには遺留分の取り扱いに注意を
遺留分とは相続人が最低限保障されるべき取り分として民法に定められている相続分の割合のことで、遺言書による指定に従って行われる相続においてのみ問題になります。たとえば遺言書において「財産のすべてを配偶者に相続させる」という指定があったとしても、被相続人の子や直系尊属が相続人であるときは、遺言による指定を否認してみずからの遺留分を確保するよう請求することができます。これを遺留分減殺請求権と言います。
相続のことでお困りの方は、どうぞ税理士紹介タックスナイトまでお問合せください。相続税の対策、対応に強い税理士をご紹介させていただきます。

